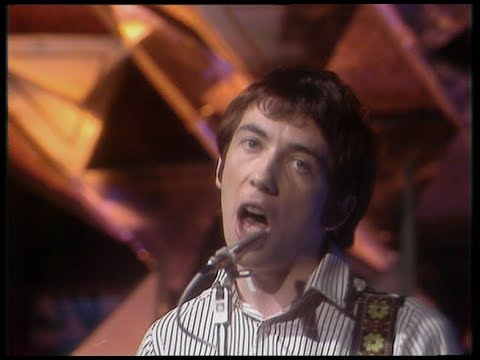【ウォーホルのバナナが描かれた1stアルバム】
SNAKEPIPE WROTE:
先週、ROCKHURRAHが書いた「残暑見舞2025」にあったように、お盆時期から約10日程手術のために入院していたSNAKEPIPE。
日本一(世界一かも)と言われている名医に執刀してもらい、無事に退院したんだよね。
手術の翌日から立って歩けたのにはびっくり!
そして退院時も、迎えに来てくれたROCKHURRAHとともに、自分の足で帰宅できて良かったよ。
皆様、お騒がせしましたが、ここにSNAKEPIPEの復活を宣言いたします!(笑)
報告に続いて、通常のブログに戻ろうか。
当ブログのカテゴリー「ふたりのイエスタデイ」で、前回書いた「ふたりのイエスタデイ chapter27 / RUN DMC」について、ご指摘を受けてしまった。
RUN DMCについては2020年2月に「ふたりのイエスタデイ chapter17 /Sigue Sigue Sputnik&RUN DMC」として記事にしている、というもの。
6年前に書いたことを失念していたとは!
ダブった記事を載せてしまい、深くお詫び申し上げます。
恥ずかしいミスだね。(笑)
気を取り直して、「ふたりのイエスタデイ」を書いていこう。
今回はヴェルヴェット・アンダーグラウンドについてだよ! ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground)は、1964年にニューヨークで結成されたバンド。
ヴェルヴェット・アンダーグラウンド(The Velvet Underground)は、1964年にニューヨークで結成されたバンド。
ロック史上、最も革新的で影響力のあるバンドのひとつとして知られているんだとか。
画像中央のルー・リードが作詞したのは、ドラッグ、セクシュアリティや暴力など、それまでは扱われなかったテーマというのが特徴なんだって。
ポップ・アーティストのアンディ・ウォーホル(画像左から2番め)が、デビューアルバムのプロデュースとアルバム・ジャケットを手がけ、アートと音楽の融合という点も画期的だったという。
ウォーホルが連れてきたとされるモデルのニコ(画像左)が1stアルバムのみヴォーカルとして参加している。
ヒップでクール(死語)な人たちが集まって、バンドやったってことだね。
SNAKEPIPEはリアルタイムで聴いていたわけではないので、伝聞としてお伝えしているよ。(笑)
ここからが思い出につながる話ね。
SNAKEPIPEの父親は、数回、写真展を開催したことがある。
展覧会場ではBGMを流すことができたので、SNAKEPIPEと長年来の友人Mが音楽を担当した。
手持ちの音源をいくつかピックアップし、父親に聴いてもらう。
その中で「これ、いいね!」と父親が選んだのが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Sunday Morning」だった。

精神世界的な映像だね!(笑)
ゴッホの絵画作品みたいな「ぐるぐる」が出てきて、とてもアートな雰囲気。
2017年にアップされたようなので、当時は観ていない動画だよ。
デビュー・アルバム「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド・アンド・ニコ」を聴きながら、父親にアンディ・ウォーホルが関係している話を伝えると、とても嬉しそうに「これに決めよう!」と瞬時にBGMが決定した。
SNAKEPIPEはCDを所持していなかったので、父が購入し、展覧会場で使用することになった。
その時のCDを今でも所持していて、愛聴しているよ!(笑)
父親の展覧会場で、SNAKEPIPEは受付に立っていた。
ふらっと立ち寄った外国人(欧米人)から英語で尋ねられる。
「この曲のタイトルは?」
展覧会のテーマにした「Sunday Morning」だったので、CDジャケットを見せて説明する。
「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、OK!サンキュー!」
暗記するように何度もバンド名をつぶやき、お礼を言って去っていった。
写真展についてのやり取りをしているのかと、父親が駆け寄ってきたけれど、質問が音楽だと分かり落胆していたっけ。(笑)
 NHKで再放送されていた「ヴェルヴェットの奇跡 革命家とロックシンガー」を観る。
NHKで再放送されていた「ヴェルヴェットの奇跡 革命家とロックシンガー」を観る。
1989年にチェコスロバキアが革命により、共産党政権が崩壊し民主化が始まる。
チェコの反体制派から熱烈な指示を受けたのが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの1stだったという。
後にチェコ大統領となるヴァーツラフ・ハヴェルが偶然手にしたレコードが革命の始まりだったとされ、「ヴェルヴェット革命」と呼ばれているという。
「音楽が歴史を変えた」ドキュメンタリーで、とても興味深かったよ!
大統領になったハヴェルが衝撃を受けたのが「I’m Waiting For The Man」だったという。
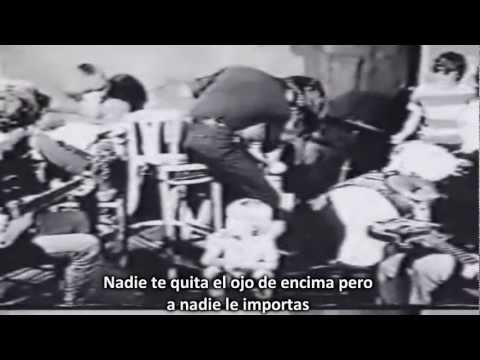
ピンボケで、ズームのスピードが速いため、かなり見づらい動画だよ。
SNAKEPIPEは洋楽を日本盤で買うことがほとんどないので、対訳が載っている解説を読んだことがない。
「I’m Waiting For The Man」はどんな内容なのか調べてみようかな。
マン(The Man)=麻薬の売人に会うために、26ドル握りしめレキシントン通りの125番地に向かう俺。
ここは白人の俺にとって居心地が悪い場所。
好奇の目で見られたり、何をしに来たのか探られてしまうからさ。
気にせず「マン」を待ち続けて、ようやく「マン」がやってくる。
待たされた挙げ句やっとドラッグにありつき、安心して帰路につけたよ。
少しSNAKEPIPEの脚色が入っているけど、歌詞を要約するとこんな感じみたい。
タイトルは「売人を待つ」というスラングで、当時の26ドルは、今だと200〜250ドルくらい。
これはヘロインの相場だったらしいね。
まるでスナップショットのように街の様子を切り取り、ドラッグをテーマにした曲は斬新だったんだね。
ヒッピーが提唱する「愛と平和」とは一線を画してるよ。
まさにバンド名通り「隠れた世界」や「社会の裏側」を表現していることが分かるね。
ROCKHURRAHがデビュー・アルバムの中で好きな曲は「Venus In Furs」だって。
タイトルはマゾッホの小説「毛皮を着たヴィーナス」から取られている曲なんだね。
ジョン・ケイルのエレクトリック・ヴィオラが印象的だよ!
ROCKHURRAHはジョン・ケイルが好きで、レコードを数枚所持しているという。
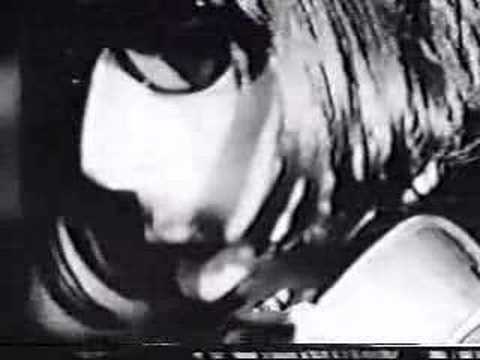
こちらもピンボケの粗い画像だけど、当時の雰囲気が感じられるよね。
ウォーホルが関わったことでアートと音楽が融合されたことは前述したけれど、文学的要素も加わっているよ。
80年代日本でバンド名に「マダム・エドワルダ」と名付けたり、「ジュネ」を名乗ったりするのも同じ傾向だよね。(笑)
文学と音楽とファッションとアートなど、複数の要素を「たしなんで」いたのは、80年代の共通項だったのかもしれない。
SNAKEPIPEもROCKHURRAHも然り、だからね!
 2023年3月に「合田佐和子展」を鑑賞し、ルー・リードのアルバム・ジャケットを手がけていたことを知る。
2023年3月に「合田佐和子展」を鑑賞し、ルー・リードのアルバム・ジャケットを手がけていたことを知る。
合田佐和子はかねてよりルー・リードのファンで、1975年に来日した際、インタビューをしたという。
気難しいルー・リードと打ち解け、1977年に発売されたベスト盤(日本盤)アルバム・ジャケットの依頼を受けた話が紹介されていたっけ。
合田佐和子が出会った時には、すでにヴェルヴェット・アンダーグラウンドは解散していて、ソロ活動していたんだね。
ルー・リードについて調べていたら、2008年に前衛音楽家のローリー・アンダーソンと結婚していたことを知ったよ。
今頃驚くのは、遅過ぎだよね。(笑)
今回はヴェルヴェット・アンダーグラウンドにまつわる思い出話と曲の紹介をしてみたよ。
曲を聴いたりにおいをかいだりして、ふと昔の記憶が蘇ってくることがあるよね。
やっぱり歳だからかな?(笑)