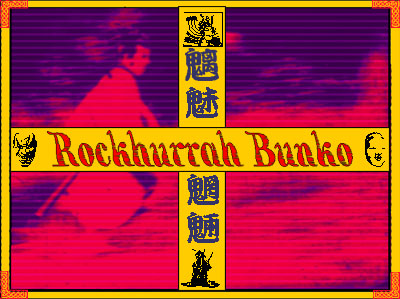 【国枝史郎伝奇文庫風にROCKHURRAHが勝手に制作】
【国枝史郎伝奇文庫風にROCKHURRAHが勝手に制作】
ROCKHURRAH WROTE:
少年時代から現在まで趣味嗜好の根本がほとんど変わってないROCKHURRAHだが、今でも大事に持っているものは意外なことに、かつてコレクションしていたアナログ・レコードとかではなくて子供の頃に買った本だったりする。
レコードの方はパソコンで録音してCDにするというデジタル化での保存が比較的簡単に出来る(敢えてそういう事をしないのが真のコレクターなんだろうが、それは置いといて)から、よほどの宝物以外は手放して「あぁ惜しかった」という程にはならない。
ところが本の方は今まで何度もしてきた引越しの際に手放してしまったものが多く、その後新たに入手出来ずに困ったという経験も多いのだ。最近の古本屋事情もないものは徹底的にない、あるものはどこにでもある、という寒い状況。掘り出し物も滅多に見つからないときてる。自力でデジタル化も難しいしね。
そういう自分の書棚を改めて眺めると圧倒的に戦前戦後の古い探偵小説ばかり。ミステリーと言うより推理小説と言うより探偵小説と呼ぶ方がしっくりくるような作家群だ。それだけなら主義の一貫した奴でいいんだが、パンクでサイコビリーでホラー映画好きで探偵小説好きで裁縫や料理もちょっぴりこなす奴となると随分同志の人口は減ってくるだろうか?完全に同じ嗜好の人もまだまだいるかな。
前置きがとても長かったが、今回はその書棚の中から選んだ2冊の古びた本から話を進めようか。

「国枝史郎伝奇文庫 神州纐纈城」上下2巻だ。
数々の引越しでも絶対に手放さなかった少年時代からの宝物だ、って程にはそこまで貴重なものでもないが。
これは講談社が昭和50年代に出してた文庫で全28巻より成る国枝史郎の集大成、横尾忠則による装幀も素晴らしい。
多少はマニアックでも入門者にやさしい内容を心がけるrockhurrah.comであるから「国枝史郎って誰?」という現代っ子(この言葉がすでに死語か?)でもわかるように簡単な説明をしておくか。
国枝史郎は大正から昭和初期にかけて活躍した作家で主に伝奇小説と呼ばれるジャンルで類を見ない独創性を誇り、人気があった。ごく簡単に言えば日本独自の怪異とかファンタジーっぽいものを主題にした時代小説で燦然と輝く作品を描いたのがこの作家なのだ。決してエジソンとか二宮金次郎とか偉人を描いた伝記小説ではないので間違えないように。
この人が書いた小説の中で最も有名なのが「蔦葛木曽棧(つたかずらきそのかけはし)」「八ケ嶽の魔神」そして前述の「神州纐纈城(しんしゅうこうけつじょう)」の三大傑作だ。中でも「神州纐纈城」の素晴らしさは現代でも色褪せる事はない。
武田信玄の家臣、土屋庄三郎が出会った一枚の深紅の布「纐纈布」。
人間の生き血を絞り染めたという禍々しい布に誘われて庄三郎は武田家をドロップアウトしてしまう。要するに不思議な力で勝手に宙を舞う布を追っかけているうちにこの人は行方不明になってしまうのだ。現代社会で言えば無断欠勤で馘首といったところだろうが、戦国時代であるからして勝手にふらふら他国に行かれてしまっては困る。そこで信玄が庄三郎探索に差し向けた刺客が高坂弾正の庶子、高坂甚太郎なる凄腕の少年武士。鳥もちの竿を自在に操る武器とするやたら強い悪ガキだ。
富士山の麓を舞台にこの二人の追いつ追われつの物語になるのかと思いきや、予想は見事に覆されてどんどん場面は変わって、さらに出てくる登場人物のアクの強さ、奇っ怪さは増してゆく。「富士に巣くう魑魅魍魎」などと謳い文句に書いてある通り、妖怪などは出ないが人間こそが一番恐ろしい魑魅魍魎として描かれている。
富士山の麓に住む三合目陶物師(すえものし)と呼ばれる男。人を襲って陶器を焼く竃で処分してしまうという恐ろしい腕前の残忍な美形盗賊だ。
富士の洞窟の中で奇怪な造顔術(今で言う整形手術)を行う謎の美女、月子。罪業を背負った人々を整形し別人に生まれ変わらせるという闇商売をしている。
そしてタイトルにある通り登場する纐纈城と仮面の城主。富士の麓に住む人間をさらって来て冒頭に出てきた纐纈布を作るために生き血を絞り、染色する工場を持つという邪悪の総本山で、人工の水蒸気に隠され本栖湖の真ん中にある。城主は触れる者全てを一瞬で崩れた病人にしてしまうという「奔馬性癩患(ほんばせいらいかん)」なる恐ろしい病気の持ち主。醜い病気を隠すために能面を付けているのだ。
一方その纐纈城と対峙する富士教団神秘境。慈悲の心を持った救世主、光明優娑塞(こうみょううばそく)を勝手に教祖と仰ぐ狂信者の巣窟だ。
これらの主要登場人物が入り乱れてさらにその他大勢(剣聖塚原卜伝までも)登場するのだが、高坂甚太郎はこの纐纈城に導かれて囚われ、土屋庄三郎は富士教団神秘境へと彷徨い込んで、この二人は出会う事がない。
後半はなぜか激しい郷愁を感じた纐纈城主が遂に城を出て、人々を「祝福」しながら甲府に向かうという掟破りの展開。
素早い場面転換と複雑で奔放なストーリー、話はどんどん膨れ上がり脱線してしまい、この伝奇小説の裏バイブルのような作品は残念ながら未完のまま終わってしまう。
にも関わらず「神州纐纈城」は国枝史郎の最高傑作と呼ばれ、三島由紀夫をはじめ、後の時代の数多くの人たちにリスペクトされた。
ストーリー紹介になってなかったが読んでない人で興味を持ってくれる人も多いはず。何と大正14年の作品だよ、これ。
活劇映画もTVも漫画もアニメもTVゲームもなかった時代にこれを読んだ人が受けた衝撃は凄かったんじゃなかろうかと思える。ちょっと読んだだけでも誰でも映像が浮かんでくる程の妖しい魅力を持った小説だ。もともと大衆演劇畑出身の作家であるから映像的な描写やスピーディな場面展開はお手の物なんだろうが、今の人が想像するよりもずっと進んでた大正時代なんだね。
ROCKHURRAHの説明がヘタなので今時のアニメとかではありがちの舞台設定に感じてしまうだろうが、独特のリズム感溢れる名文とほぼ全ての登場人物に見え隠れするダークサイドな部分、読者の想像力をかきたてるような中途半端な終わり方が素晴らしく、不思議と子供っぽい部分はない。
話が大きくなりすぎて収拾がつかなくなり未完、と言えば昔の永井豪の漫画を思い浮かべてしまうが、まさに国枝史郎の小説は漫画向け(実際に永井豪と縁の深い石川賢が漫画にしている)と言える。がしかし、頭の中の映像化は簡単だがこの小説は数々のタブーなものがひしめいているので、実際の一般向け映画なりゲームなりには難しいかも知れない。タブーの部分を抜きにしたらこの作品の魅力は半減してしまうだろうから。でも、個人的にはぜひ誰か映像化に挑戦して欲しい(原作に忠実に)作品だ。
ちなみにSNAKEPIPEの昔の知り合いに纐纈さんという人がいたらしいが、本当にそんな名字あるんだね。纐纈城主の名字は纐纈ではないと思うけど羨ましい。画数が多くて難しいから何度も名前を書かなきゃならない場合は大変らしい。
代表作の中でちゃんと完結していて最もまとまりが良い「八ケ嶽の魔神」になるとさらに登場人物の暴走が激しく、読んでいて笑ってしまう部分もあるほど。
親の因果が子に報い、というこの手の小説にはお決まりの数奇な運命にある呪われた主人公、鏡葉之助(幼名猪太郎)の大活躍、というよりは暴れっぷりを描いた小説で「神州纐纈城」のような大傑作と比べるとかなり粗削りではあるんだが、これはこれで「凄い」と思える、ある意味アナーキーな作品。これまた大正時代に書かれたとは思えないような文体。筒井康隆がかつて「時代小説」という短編で国枝史郎をパロディにしていて、原典を知っていたら大笑い出来る内容だったのを思い出す。
さてさて、これからもう一つの長編「蔦葛木曽棧」についても書こうと思ったのだが、ここまで書いていて正直疲れてしまったので今日はここまでという事にしておこう。
それではごきげんよう。
(未完)




